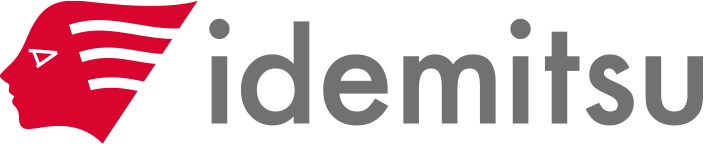公開日:

脱炭素とは?
企業が知っておくべき基本情報と取り組み事例
脱炭素社会が注目されていることは知っていても、そもそも「脱炭素とは何か」「企業担当者として何からはじめればよいのか」といった戸惑いを抱えている方もいるのではないでしょうか。
脱炭素とは、気候変動を引き起こす温室効果ガス(GHG)の一つ、二酸化炭素(CO2)の排出を実質ゼロにする取り組みを指します。本記事では脱炭素の基礎から企業が取るべきステップを解説します。さらには、出光興産が提案する脱炭素に向けた総合サポートを紹介します。
目次
脱炭素とは?世界で求められる理由

そもそも脱炭素とは何なのか、カーボンニュートラルとはどう違うのか、そして、なぜいま脱炭素が求められているのかを解説します。
脱炭素とは何か?カーボンニュートラルとの違い
脱炭素とは、地球温暖化の最大要因とされる二酸化炭素(CO2)の排出量をできるかぎり削減し、最終的にゼロを目指す取り組みを指します。似た言葉に「カーボンニュートラル」がありますが、こちらは森林吸収などによるCO2吸収量を含めた概念で、排出量と吸収量を均衡させ、実質的な排出量をゼロにするという考え方です。
なぜいま脱炭素が世界で求められているのか
世界の平均気温は産業革命前と比べて上昇しており、豪雨や熱波などの異常気象が深刻化しています。このまま放置すれば海面上昇や食料危機が進み、企業活動にも大きな影響がおよぶ懸念があります。また、石油や石炭など化石資源には埋蔵量の限界があり、価格高騰や供給リスクも顕在化しています。持続的成長を図るうえで脱炭素は最優先課題となっています。
脱炭素に向けた国際的な取り組み
現在、世界では共通の枠組みを設け、技術と政策で脱炭素に向けた取り組みを加速しています。
国際社会の目標
2015年に採択された「パリ協定」では、国際ルールとしてすべての締約国が温室効果ガスの削減目標を持ち、5年ごとの更新を定めています。世界共通の長期的な目標として、「産業革命前より世界の平均気温上昇を2度未満、できれば1.5度以内に抑える」ことを掲げています。その達成へ向け、「各国は温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には温室効果ガス排出量と吸収量のバランスをとる」としています。
世界が進める主要な脱炭素施策
パリ協定の目標を後押しするため、各国は多角的な技術導入を進めています。例えば、再生可能エネルギー(再エネ)の活用は脱炭素化において重要な役割を果たします。太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど多彩な発電方式がありますが、各国の資源や気候に合わせて組み合わせることで電源構成の脱炭素化を推進しています。
さらに、火力発電や産業炉で水素やアンモニアを混ぜて燃焼させる実証試験も進行中です。これらは燃焼時にCO2をほとんど出さない次世代燃料として期待されています。モビリティ分野では電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)が徐々に増え、国際航空輸送分野でも持続可能な航空燃料(SAF)の導入が本格化しています。
脱炭素に向けた日本の取り組み

ここからは日本政府の目標と現在の課題、企業に求められることについて解説します。
日本の目標と政府の取り組み
政府は2020年10月、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すと宣言しました。目標としては、2030年度において2013年度比46%削減としています。2025年2月にはさらに野心的な目標として、「2035年度、2040年度において温室効果ガスをそれぞれ2013年度比60%、73%削減」とした、新たな「国が決定する貢献(NDC)」を国連に提出しています。
また、電源構成について、政府は2030年度に再エネの比率を36〜38%に引き上げることを目標としています。第7次エネルギー基本計画(2025年2月閣議決定)においては2040年度には40〜50%へ引き上げる方針が表明されました。
日本の課題
2023年度の時点で、国内発電の電源構成は68.6%を火力が占め、再エネ比率は22.9%にとどまっているのが実情です。石油や石炭、液化天然ガスへの依存が続くなか、電源構成の脱炭素化は急務です。また、部門別の排出量をみると、産業部門だけで国内CO2排出の3割近くを占め、製造業、鉱業、建設業、農林水産業などの適切な対策が不可欠とされています。
企業が取り組むべき脱炭素経営とそのメリットとは?

日本の政策目標を踏まえ、企業はどのような取り組みを行うべきなのか。ここでは脱炭素経営とは何か、企業にとってのメリットや注意点を紹介します。
脱炭素経営とは
脱炭素経営とは、「気候変動対策の視点を織り込んだ企業経営のこと」を指します。具体的には、気候変動対策を自社の経営上の重要課題と捉え、事業活動で排出される温室効果ガスを継続的に測定し、省エネや再エネ導入などで削減しながら、最終的に排出量を実質ゼロへ近づける企業経営です。グローバル企業を中心にRE100(再エネ100%宣言)やSBT(科学的根拠に基づく削減目標)などの脱炭素経営に向けた取り組みが広がっています。環境省の「中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック」では、脱炭素経営によって、グローバル企業だけでなく多くの国内企業がメリットを得られるとしています。
脱炭素経営が注目されている理由
この背景にあるのが、情報開示ルールの強化です。
温室効果ガス排出量を分類する際の概念にScope1(自社が直接排出)、Scope2(他社から購入の電力などから排出)、Scope3(原材料調達・物流・使用段階など自社以外の間接排出)があります。
ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)は、2023年にScope3を含めた気候関連情報の開示義務化を確定しました。日本でも、SSBJ(サステナビリティ基準委員会)が開示基準を2025年3月に公表し、2026年3月期の有価証券報告書から適用できる見通しです。今後は「供給網全体で排出量を可視化し、削減計画を示すこと」が重要になり、取引先からScope3にかかわる情報の提示や削減についての要請が増える可能性があります。
脱炭素経営のメリット
企業が脱炭素経営に取り組むメリットはさまざまありますが、ここでは2つの側面から解説します。
企業ブランド力向上による優位性の構築
削減目標を公表し達成状況を開示することは、企業にとって気候変動対策への前向きな姿勢を示せるため投資家の信頼が高まります。例えば、ESGファンド(環境・社会・ガバナンスに優れた企業を選別して投資するファンド)に組み入れられることで、国内外の機関投資家からの資金流入が期待できます。
コスト削減と生産性向上
省エネ設備への更新や工場・オフィスなどの高効率運営により、電力・燃料コストの低減が見込めます。光熱費削減で生まれた資金を新たな投資に回せるうえ、社会的意義のある脱炭素への取り組みを共有することで、従業員エンゲージメントが向上し生産性アップも期待できます。
注意点
脱炭素の取り組みには、設備の初期投資などの経済的負担が必要となる場合があります。資金計画や中長期的な費用対効果、上述の効果を総合的に評価し、計画的に取り組みを進めていくことも必要です。
脱炭素経営のために企業ができる具体的な取り組み
ここでは脱炭素経営を具体化する3つの実践ステップを、現場で取り組みやすい順に見ていきましょう。
目標の策定と公表
最初に行うのは自社の現状把握とターゲット設定です。まずはScope1、2を中心にCO2排出量を算定し、必要に応じて供給網全体を含むScope3の主要カテゴリを洗い出します。そのうえで、「2030年までに40%削減」など中長期の数値目標を経営戦略に組み込みます。目標は自社サイトや統合報告書で公表し、達成状況を毎年アップデートすると投資家や取引先からの信頼が高まります。
エネルギーの削減、再エネの創出(太陽光他)
目標の策定を行ったあとは、具体的な対策を検討します。主な対策としては、エネルギーを「減らす」「替える」「創る」「貯める」方法が挙げられます。例として、「減らす」は事業活動に必要な設備の効率化や空調/照明の節電推進、エコカーへの乗り換え、「替える」は電力契約を再エネプランに変更、「創る」は施設の屋根上に太陽光パネルを設置し発電した電力を自家消費、「貯める」は蓄電池やEVを導入し効率よくエネルギーを活用、などが考えられます。
対策の実践と公表
3つ目のステップは実際に対策を実践し、その効果を公表することです。
例えば、「減らす」に取り組んだ場合、実際のエネルギー削減量だけでなく、CO2削減量に換算した実績も積極的に見える化しましょう。また、「替える」に取り組んだ場合は、環境価値を証明する証明書(例:非化石証書)を活用して、自社の取り組みを公表しましょう。
脱炭素に向けた企業の取り組みの事例
脱炭素の実践方法は業種や立地によって千差万別ですが、ここでは都市型小売チェーンが再エネをオフサイトPPAで調達した事例を紹介します。
まいばすけっと株式会社(イオングループ)様
首都圏でコンビニサイズの食品小売店を展開するまいばすけっとは、グループ方針として「店舗電力を2030 年までに再エネ50%、2040年までに100%」へ引き上げる目標を掲げています。ところが都市部の店舗は屋根面積が限られる、ビルの一部に入居しているなど、自社で太陽光発電を導入しづらいという課題がありました。そこで採用したのが低圧契約によるオフサイトPPAです。これは店舗とは別の土地に出光興産がまいばすけっと専用の小型太陽光発電所を新設し、発電した電気を購入する仕組みです。これにより、都市部でも太陽光発電を活用した脱炭素化の取り組みを実現しています。
導入事例の詳細は、以下のページをご覧ください。
脱炭素に向けたニーズに応える出光でんき
出光興産では、多様化するニーズに寄り添いながら脱炭素推進のためのさまざまなソリューションを用意しています。
GHG(温室効果ガス)排出量の見える化
脱炭素の第一歩は「現状を正しく把握する」ことです。出光興産のGHG見える化サービスは、Scope3を含んだ排出量を手間なく簡単に算定し、可視化できます。複数の見える化サービスを用意しているので、「自社内のGHG排出量を一元管理したい」「Scope1~3まで全部計算したい」など個別の要望への対応も可能です。GHG排出量が明らかになることで実効性のある削減計画の策定・実行管理へとつなげられます。
GHG見える化サービスの詳細は、以下のページをご覧ください。
出光興産の「GHG見える化サービス」を詳しく見るカーボンニュートラルを推進した電力プラン
出光興産の法人向け電力サービス「出光でんき」には、事業者様向けとして「出光でんき(特別高圧・高圧)」と「idemitsuでんき(低圧)」の2プランがあります。それぞれでCO2排出量削減をサポートする以下のオプションを用意しています。
- プレミアムグリーンプラス(CO2フリー):再エネ(FIT電気含む)電源と非化石証書(再エネ指定)の組み合わせで再エネ100%電気を使用できるプラン
- グリーンプラス(CO2フリー):非化石証書(再エネ指定)を利用することで実質的に再エネ100%の電気を使用できるプラン
- カーボンミニ(特別高圧・高圧のみ):排出係数を0.200kg-CO2/kWh以下に抑えた低炭素プラン
出光でんき(特別高圧・高圧)
オフィスビルや工場、病院などの大・中規模施設を運営する法人向けのプランです。通常のスタンダードプランに加えて、脱炭素に取り組む事業者向けのプランも複数提供しています。
また、燃料費調整額に市場価格調整項を含まない料金体系によって電気料金の変動を抑制しています。
出光興産では、各地に火力・バイオマス・風力・太陽光・地熱と、さまざまな発電方式の発電所を運営し、安定した電力調達を実現しています。全国(沖縄と離島を除く)の大中小さまざまな規模の施設への供給実績も豊富です。
電力プランの詳細は、以下のページをご覧ください。
出光でんき(特別高圧・高圧)のプランを詳しく見る
idemitsuでんき(低圧)
idemitsuでんきの料金プランは、「Sプラン(従量電灯プラン)」と「低圧電力プラン(動力プラン)」の2種類です。
「Sプラン」は、照明器具や小型の電化製品など電灯用のプラン、「低圧電力プラン」は、業務用のエアコンや冷蔵庫、モーターなど、動力用のプランです。
加えて、環境に優しくエコな電気に切り替えられる再エネオプションも提供しています。
各電力プランの詳細は、以下のページをご覧ください。
idemitsuでんき(低圧)のプランを詳しく見る
再生可能エネルギー100%電力供給証明書の発行
プレミアムグリーンプラス(CO2フリー)またはグリーンプラス(CO2フリー)のオプションプランを契約すると、出光興産が独自に発行する 「ご利用証明書」(サンプル下図)を受け取れます。これは、事務所やHPに掲示することで、対外的にも自社取り組みの紹介として活用いただいております。
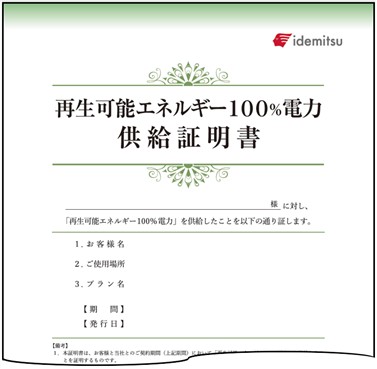
※画像はイメージになります
脱酸素社会に向けた世界的な取り組みを理解して段階的に対策をはじめよう
CO2排出を実質ゼロに近づける取り組みは、世界共通の課題となっています。日本政府も2050年カーボンニュートラルを掲げ、再エネ比率拡大や情報開示強化を推進中です。企業は脱炭素に向けた取り組みを段階的に進めることでブランド力を高めることができるでしょう。近年は、脱炭素目標を掲げ取り組みを開始する企業も増えてきています。出光興産ではGHGの可視化ツールや再エネを使用した電力プランなど「脱炭素ソリューション」を通じて、企業の脱炭素経営を総合的に支援します。
出光でんきだからこそ実現できる、安定した電力調達を提案します。