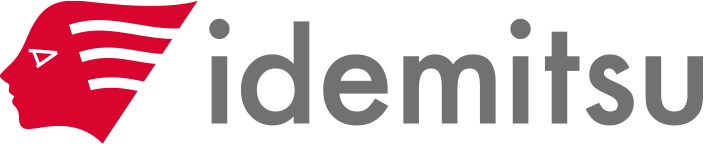公開日:

力率とは?
定義や力率割引・割増の計算方法について解説
電気料金の請求には「力率割引」が適用されていることがあります。しかし、そもそも力率とは何なのか、そして力率割引とはどのような仕組みなのか気になっている方も多いでしょう。
本記事では、力率の概要や力率割引の意味、力率改善のメリット、力率割引・割増の計算方法などについて解説します。
目次
力率の定義

力率とは
発電所から送られてくる電力は、受電後、実はすべてを有効に使い切れているわけではありません。実際には、機器内部で有効に使われない電力が存在します。
力率とは、発電所から送られてくる電力のうち、有効に使われる電力の割合を示した数値です。
交流電力の種類
電気の流れ方には直流・交流の2種類があり、家庭などで使われる電気は交流電力です。そしてこの交流電力は有効電力、無効電力、皮相電力の3つに分類できます。
| 交流電力 | 有効電力 | 発電所から供給された電力のうち、実際に負荷で消費される電力 |
| 無効電力 | 発電所から供給された電力のうち、負荷で消費されない電力 | |
| 皮相電力 | 発電所から送られる電力の総量 |
力率によってわかること
力率は皮相電力のうち有効電力が占める割合を表すため、以下の式で求められます。
力率 = 有効電力 ÷ 皮相電力
力率は%または0から1までの範囲で表され、皮相電力のすべてが有効に消費された場合、力率は100%(1.0)と考えます。
力率が高いほど無効電力が少なく、電力を効率的に使えていると判断できます。
力率改善のメリット

力率改善とは、無効電力を減らして力率をできるだけ高くする(100%に近づける)ことです。力率改善には以下のメリットがあります。
電気設備への負荷を減らしコスト削減につながる
力率が低いと、必要な有効電力を得るためにより多くの電力を送ることになり、電気設備にかかる負荷が大きくなってしまいます。
例えば、動作に100Wが必要な機器に電力を供給する場合、力率50%だと力率100%の場合と比べて2倍の皮相電力が必要です。力率50%は極端な例ですが、流れる電流が多いほど変圧器や配線などで発生する熱も増えるためかかる負荷が大きくなってしまうのです。
これを軽減できれば、その分設備交換や新しく設備を増やす必要が減るため結果としてコスト削減にもつながります。
また、力率が高いと電気料金の割引を受けられることもあります。次項では、この割引について詳しく解説します。
力率割引と力率割増

電気料金の請求には、「力率割引」や「力率割増」が適用されていることがあります。電気の基本料金は力率が一定の基準を上回ると割引、下回ると割増されるため、仕組みを理解しておくことが大切です。それぞれの意味や計算方法は次のとおりです。
※力率割引の有無はご契約のプランによって異なります。
力率割引と力率割増
電力会社は、力率が高いほど余分に電力を供給せずに済みます。高力率で電気を使用してもらうために、力率の高い利用者(需要家)には割引を適用し、力率の低い需要家へは割増を適用しているのです。
一般的に、力率が85%を上回るときに適用される割引を「力率割引」、85%を下回るときに適用される割増を「力率割増」といいます。
力率割引・割増を含めた計算方法
力率割引・割増を含めた基本料金を求める式は、以下のとおりです。
基本料金 = 契約電力 ✕ 基本料金単価 ✕(1.85 - 力率(%)÷ 100)
この式の「1.85-力率(%)÷100」の部分が力率割引・割増を計算する補正係数になります。
1.85とは力率が85%(0.85)のときに計算結果が1.00になる、つまり割引も割増もない状態にするために設定された値です。
力率70%・85%・100%の3パターンを例に、力率割引・割増を含めた基本料金の計算方法を説明します。
| 力率 | 70% | 85% | 100% |
|---|---|---|---|
| 補正係数 | 1.85-70÷100=1.15 | 1.85-85÷100=1.00 | 1.85-100÷100=0.85 |
| 基本料金の計算式 | 基本料金=契約電力×基本料金単価×1.15 | 基本料金=契約電力×基本料金単価×1.00 | 基本料金=契約電力×基本料金単価×0.85 |
| 力率割引・割増 | 1.15倍(15%割増) | 1.00倍(割引・割増いずれもなし) | 0.85倍(15%割引) |
【力率70%の場合】
補正係数:1.85-70÷100=1.15
補正係数が1.15となり、基本料金は以下のように1.15倍(=15%割増)になります。
基本料金=契約電力×基本料金単価×1.15
【力率85%の場合】
補正係数:1.85-85÷100=1.00
補正係数が1となり、基本料金は以下のように割引も割増も適用されない状態です。
基本料金=契約電力×基本料金単価×1.00
【力率100%の場合】
補正係数:1.85-100÷100=0.85
補正係数が0.85となり、基本料金は以下のように0.85倍(=15%割引)になります。
基本料金=契約電力×基本料金単価×0.85
補正係数が0.85となり、基本料金は以下のように0.85倍(=15%割引)になります。
このように、力率が基本料金に影響する契約の場合、電気料金の変動要素となります。電気料金の請求書において、基本料金の請求額が「契約電力×基本料金単価」と一致しないときには、力率割引または割増が適用されていると考えられます。
電気料金を節約する4つの方法

力率改善以外にも電気料金を節約する方法があります。
照明・空調などを省エネ性能の高い機器に交換する
オフィスビルの場合、消費電力の多くを占める設備として照明・空調が挙げられます。これらを省エネ性能の高いものに交換することも一つの方法です。
照明設備をLEDに交換することで、消費電力を蛍光灯の約3分の1、白熱電球の約8分の1まで削減できるため、電気代がその分安くなります。また、エアコンや冷蔵庫・冷凍庫、複合機などは、古い機種ほど消費電力が多いとされています。これらも省エネ性能が高い最新機種に交換することで、電気代の節約につながるでしょう。
節電を意識する
エアコンの設定温度を適温にする、ブラインドやカーテン、遮光・遮熱フィルムなどを季節によってうまく使い分ける、照明自体を間引きするなどの方法も節電効果があります。
また、小売店やスーパーなどでは空調や照明以外にも、冷蔵庫・冷凍庫やショーケースなど消費電力が大きい設備があります。これらの設定温度を見直す、吸い込み・吹い出し口に商品を置かない、冷気が漏れないようビニールカーテンを設置するなども有効な手段です。
日々の積み重ねが節電の第一歩になるので、周辺環境の見直しなどあらためて意識してみましょう。
自社で電気を作る
自社で電気を作る自家発電も一つの方法です。自家発電設備は初期費用や維持コストはかかりますが、電気料金の削減だけではなく、災害や事故が起こった際の備えとしても有効です。
すでに普及している自家発電の代表例として、自社の屋上や外壁、敷地などを活用してソーラーパネルを設置する「太陽光発電」が挙げられます。太陽光発電は、発電時にCO2を排出しないため、脱炭素への取り組みにも貢献できます。
自社に最適な電力会社や料金プランを選ぶ
電気料金を安くするには、電力会社の切り替えや料金プランの見直しも検討してみましょう。
電力自由化によって、現在は法人・個人を問わず需要家が電力会社や料金プランを自由に選べるようになりました。これにより多くの小売電気事業者が、多様な料金プランやサービスを提供しています。
電力会社やプランの見直しは、省エネ設備の導入のように大きな初期コストをかける必要がない点もメリットです。
最後に、電力プランの選択肢の1つとして、出光興産の「出光でんき」を紹介します。
「出光でんき」は、オフィスビルや工場、病院など大・中規模施設を運営する法人向けの、特別高圧・高圧プランです。出光興産は自社で大型の火力発電所、太陽光や地熱をはじめとする再生可能エネルギー電源を運営していることから、電力を安定的に調達できることも特徴です。
さらには、脱炭素に取り組める「プレミアムグリーンプラス」など4種類のプランがあり、多様なニーズに合わせた適切なご提案が可能です。
また、燃料費調整額に市場価格調整項を含まない料金体系のため、電気料金の変動幅を抑制しやすいことも特徴です。
出光でんき(特別高圧・高圧)のプランを詳しく見る力率割引を理解して電気料金を正しく把握しよう
力率とは、発電所から送電された電力に対して、有効に使われた電力の割合です。電力会社は、力率によって電気料金の割引(力率割引)や割増(力率割増)を行なうことがあるため、力率は電気料金を正しく理解するうえで重要な要素といえます。
力率は、設備の見直し等によって改善することができます。
すでに力率100%に達している施設で、電気料金を見直したい方には、省エネ機器の導入や電力会社・料金プラン切り替えの検討をおすすめします。
この機会に、自社の電力使用状況や契約プランを見直してみてはいかがでしょうか。
出光でんきだからこそ実現できる、安定した電力調達を提案します。