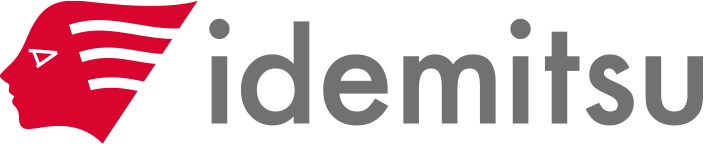公開日:

再エネ賦課金とは?
仕組み・計算方法から今後の推移、法人ができる対策について解説
企業のコスト管理を担当されている方なら、毎月の電気料金明細を見て「再エネ賦課金とは何なのか、今後どうなるのか」と疑問に思われたことはないでしょうか。
再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及を目的とした国の制度に基づくもので、すべての電力利用者が負担しています。仕組みを正しく理解することで、電気料金への影響も考慮することができるでしょう。
この記事では、再エネ賦課金の基本から単価の推移、計算方法、法人が取り組める具体的な対策までわかりやすく解説します。
目次
再エネ賦課金とは?その基本を理解しよう

再エネ賦課金は、企業の電気料金に含まれる重要な費用項目です。その仕組みや目的、電気料金への影響を理解することで、今後のコスト管理に役立てることができます。ここでは、制度の背景と成り立ちを2つの切り口から紹介します。
再エネ賦課金は「再生可能エネルギーを支えるための国民負担」
再エネ賦課金の正式名称は「再生可能エネルギー発電促進賦課金」といいます。再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス)普及のために、電力利用者が使用量に応じ毎月負担する制度です。負担の対象者は、家庭・企業を問わず、国内で電気を使うすべての利用者です。「電気料金明細」や「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」には、「再エネ賦課金」「再エネ発電賦課金」などの名称で電気料金の一部として表示されています。
再エネ賦課金の背景であるFIT制度(固定価格買取制度)
FIT制度(Feed-in tariff:固定価格買取制度)とは、2012年から始まった、再生可能エネルギーで発電した電気を一定期間、国が定めた価格で電力会社が買い取る制度です。その費用の一部は、再エネ賦課金によって賄われています。
FIT制度は、再エネ発電所開発にかかる投資額を回収しやすくすることで、国内の再エネ普及促進を図ることを目的としています。
再エネ賦課金の今後の見通し

前述の再エネ賦課金の役割、そしてこれまでの単価推移を確認することで、今後の動向と経営への影響を考慮できます。ここからは、制度開始以来の推移と変動要因、そして2025年度以降の展望を解説します。
再エネ賦課金単価のこれまでの推移
再エネ賦課金は、2012年度に0.22円/kWhから開始し、2025年度には3.98円/kWhまで上昇。約13年でおよそ18倍に達しています。
年度ごとの単価は、以下のように変動しています:
| 年度 | 単価(円/kWh) |
|---|---|
| 2012 | 0.22 |
| 2013 | 0.35 |
| 2014 | 0.75 |
| 2015 | 1.58 |
| 2016 | 2.25 |
| 2017 | 2.64 |
| 2018 | 2.90 |
| 2019 | 2.95 |
| 2020 | 2.98 |
| 2021 | 3.36 |
| 2022 | 3.45 |
| 2023 | 1.40 |
| 2024 | 3.49 |
| 2025 | 3.98 |
このように、2023年度の急激な下落を除くと、上昇トレンドが続いています。
単価が変動する理由
単価変動には主に三つの要因があります。
- 再生可能エネルギーの導入量(買取量)の増加
FIT制度の狙いどおり、再エネ発電設備、特に太陽光発電設備への投資が進み、発電の買取量が増加することで、買取費用を賄うための再エネ賦課金の必要金額も増えます。
- FIT制度の買取価格の見直し
再エネの買取価格の変動も再エネ賦課金が変動する一因です。買取価格は、FIT制度の契約条件や再エネ発電設備の投資額を反映して、毎年見直されます。また買取価格の決定においては、回避可能費用※の影響も受けます。
※回避可能費用:電力会社が再エネの買い取りによって本来予定していた発電や電力調達を行わないことで免れることができた支出。
参考として、再エネ賦課金の単価決定プロセスを簡易的に解説します。
再エネ賦課金の単価決定プロセス
再エネ賦課金単価は、毎年度ごとにその年度が開始される前(通常3月頃)に経済産業大臣が設定します。算定式は以下のとおりです。
賦課金単価 =(買取費用等 - 回避可能費用等 + 広域的運営推進機関事務費) ÷ 販売電力量
- 買取費用等:新たに運転開始する再エネ発電設備および需給調整にかかる費用等
- 回避可能費用等:過去の市場価格を踏まえた回避可能費用単価を勘案して算出
- 広域的運営推進機関事務費:系統運用などの広域的調整にかかる費用
- 販売電力量:全国の年間総販売電力量の見込みに基づいた推計値
※減免費用のうち賦課金負担となる分の電力量を控除
さらに、専門家による第三者機関である「調達価格等算定委員会」が、これらの数値や仮定を審議・検討したうえで、最終的に経済産業大臣が単価を決定します。
なお、再エネ賦課金は全エリア同単価です。
2025年度以降の見通しとFIP制度への移行
再エネ賦課金の単価は2023年度に大きく下落しましたが、2024年度以降は再び上昇し、2025年度も3.98円/kWhと高水準が継続しています。回避可能費用の変動影響があるものの、今後も再エネの普及によって買取費用の増加が見込まれるため、今後の再エネ賦課金単価は上昇傾向が続くと予想されています。
なお、2022年よりFIP制度(Feed-in Premium)が開始され、FIT制度からの移行が進んでいます。FIT制度は、発電した電力を一定の価格で買い取る仕組みであることから、再エネ事業者にとって収益が安定する一方、国が買取費用を負担するため再エネ賦課金の増加要因となっています。
新しく開始したFIP制度は発電事業者が電力を市場等に販売する収入に加え、一定のプレミアム(補助額)を受け取れる仕組みとなっています。プレミアムの単価決定には、電力市場価格が影響することから、発電事業者に支払われる補助額も変動し、再エネ賦課金単価の変動要因となっています。
FIP制度は賦課金の「変動性を高める」要因となる一方で、中長期的には、市場価格が高い、つまり需要が多い時間に多く売電する再エネ事業者の収入が増える仕組みとすることで、電力全体における再エネの自立を促し、長期的には再エネ賦課金総額の抑制につなげる狙いがあります。
単価の推移や直近の状況を踏まえると、再エネ賦課金は今後も一定の高単価で推移する可能性が高く、法人にとっては再エネ賦課金を含む電気料金への対応がますます重要になります。次の章では、具体的な計算方法や自社への影響額の見方を解説します。
自社の負担額は?再エネ賦課金の計算方法
毎月の「再エネ賦課金」が自社にどれほどの負担になるのか、正確に把握するために計算方法を解説します。
再エネ賦課金の計算方法
再エネ賦課金は以下の式で算出されます。
再エネ賦課金 =使用電力量(kWh)× 再エネ賦課金単価(円/kWh)
具体的には、毎月送付される「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」に記載されている使用電力量と、同票または別紙で示される「再エネ賦課金単価」を掛け合わせるだけで、法人の負担額がわかります。
つまり、使用量が多いほど負担額も増えるため、単価だけでなく自社の電力使用量にも注目する必要があります。
法人向け電気料金の負担を軽減する方法
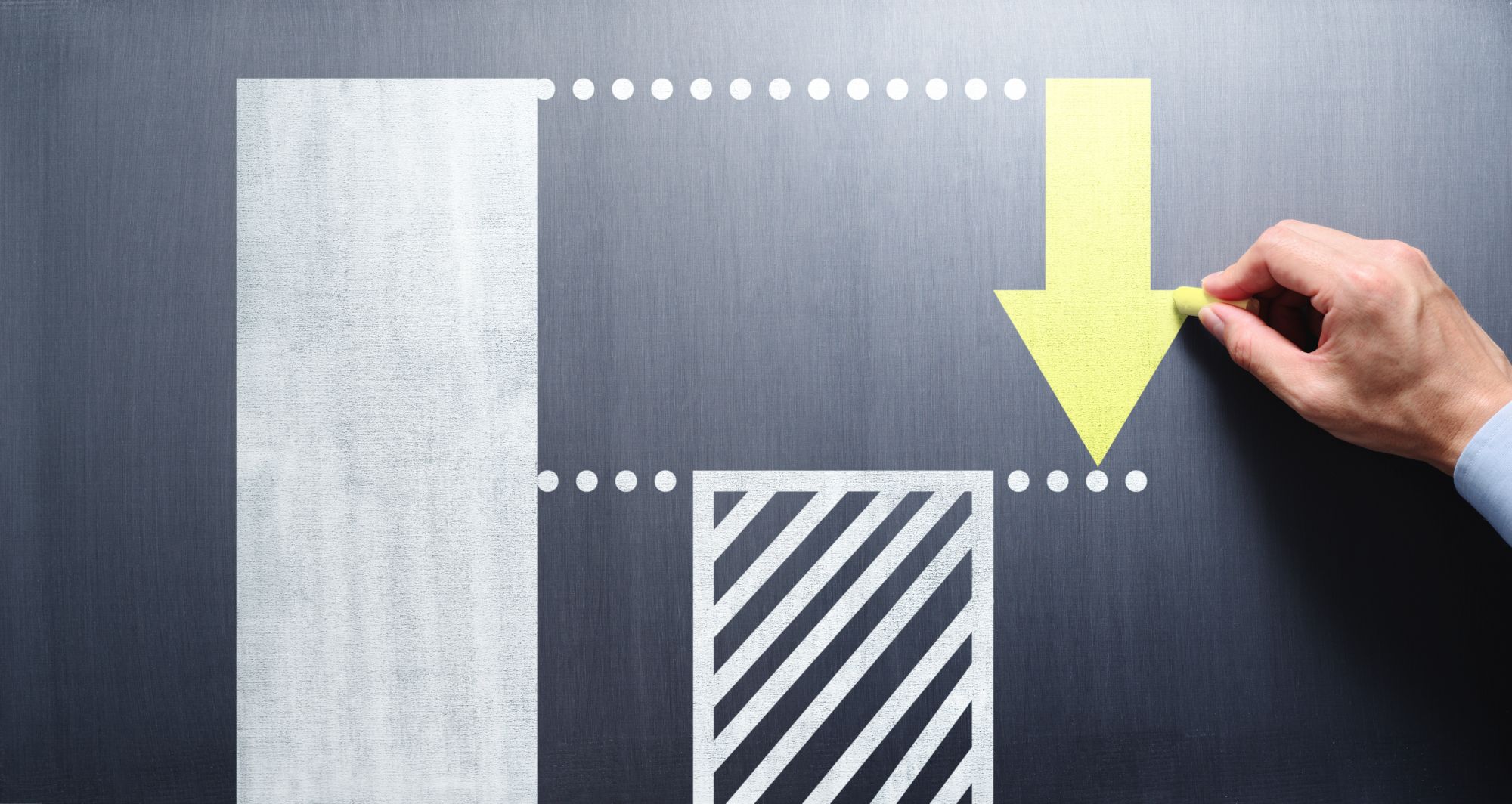
再エネ賦課金そのもの(単価)は国が定めているため、どの電力会社と契約しても一律です。そのため、削減の鍵は「賦課金対象となる使用電力量(kWh)」をいかに減らすかにあります。以下では、法人が実践できる具体的な方法を3つご紹介します。
対策1. 節電の徹底
LED照明への切り替えや空調の適切な温度設定、人感センサーやデマンド値(30分ごとの平均電力使用量)を監視するデマンドコントロールシステムの導入などで電力量の削減を図る方法があります。照明や空調の省エネ化は、従業員の判断で空調の温度を変更したり、点灯・消灯を実施したりする方法と比較して、電気使用量を着実に減らす効果が期待できます。
出光興産では空調設備を自動制御するシステムを提案しています。空調設備の交換なしで空調の過剰運転を自動で制御でき、快適性を損ねることなく省エネに取り組むことができます。空調設備の自動制御については出光興産の「空調省エネ<BEMS>」のページをご覧ください。
空調省エネ対策2. 自家消費型太陽光発電の導入
再エネ賦課金は、単なるコストととらえるのではなく、脱炭素経営への取り組みを進める契機とする考え方もあります。例えば、自社の屋根や敷地に太陽光発電システムを設置し、発電した電力を自家消費することで、購入電力量を減らすことができるため、再エネ賦課金を抑制できると同時に、CO2排出量の削減もできます。
ただし、初期投資や維持管理、屋根の強度などの導入条件に注意が必要です。
太陽光発電電力量削減と併せて検討したい、電気料金プランの見直し
再エネ賦課金単価自体は契約会社に関係なく共通で変わらないことから、削減策としては使用電力量の削減のみと言えます。ほかのコスト削減策として、現在契約している電力会社の電気料金プラン(基本料金や電力量単価)よりも、自社にとってコストメリットのある新電力会社に乗り換える方法もおすすめです。初期の機器導入やコスト負担なく実施可能で、電気料金全体を見直すことで、再エネ賦課金の負担増に伴う電気代の増加を抑制することにもつながります。注意点として、数多くの新電力会社から多様な料金プランが提供されているため、自社に合ったプランを見つける重要性を理解しておく必要があります。
電力供給と自家消費型太陽光発電など出光グループの法人向けエネルギーサービス
再エネ賦課金の上昇が懸念されるなかで、企業の電力コストを安定的に抑えるには、「購入する電気の料金プラン」と「購入電力量の削減」をバランス良く組み合わせることが重要です。出光グループでは、こうした法人の課題に応えるべく、再エネの導入から電力調達までを一貫してサポートするエネルギーサービスを提供しています。
出光でんき(特別高圧・高圧)
オフィスビルや工場、病院などの大・中規模施設を運営する法人向けのプランです。通常のスタンダードプランに加えて、脱炭素に取り組む事業者向けのプランも複数提供しています。
また、市場価格に連動する項目を含まない料金体系によって電気料金の変動を抑制しています。
出光興産では、各地に火力・バイオマス・風力・太陽光・地熱と、さまざまな発電方式の発電所を運営し、安定した電力調達を実現しています。全国(沖縄と離島を除く)の中小規模施設への供給実績も豊富です。
電力プランの詳細は、以下のページをご覧ください。
出光でんき(特別高圧・高圧)のプランを詳しく見る
idemitsuでんき(低圧)
idemitsuでんきの料金プランは、「Sプラン(従量電灯プラン)」と「低圧電力プラン(動力プラン)」の2種類です。
「Sプラン」は、照明器具や小型の電化製品など電灯用のプラン、「低圧電力プラン」は、業務用のエアコンや冷蔵庫、モーターなど、動力用のプランです。
加えて、環境に優しくエコな電気に切り替えられる再エネオプションも提供しています。
各電力プランの詳細は、以下のページをご覧ください。
idemitsuでんき(低圧)のプランを詳しく見る
脱炭素ソリューション(太陽光発電)
出光興産は、カーボンニュートラルの実現を目指す事業者の皆様に、CO2排出量の削減や再生可能エネルギー導入といった脱炭素ソリューションをトータルで提案しています。
再エネ電力プラン、温室効果ガス排出量の見える化、空調省エネ、太陽光発電、車両のEV化などお客さまの目的に合わせた最適なソリューションによって、消費エネルギーの削減を実現します。
出光興産の脱炭素ソリューションについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
出光興産の「脱炭素ソリューション(太陽光発電)」を詳しく見る出光でんき Customer Portal Site(CPS)/idemitsuでんき でんきMYページ
高圧以上の出光でんきを契約している需要家様に提供している専用サイトでは、自社の電気の使用状況が「見える化」できます。
リアルタイムの使用情報では、30分単位あるいは一日単位の使用量推移、ならびに時間帯別・曜日別の使用傾向もご確認いただけます。
また、最新の請求書・明細書、直近24ヵ月の電気使用実績のダウンロードや、電気料金、そのほか詳細情報の表示も可能です。自社で節電対策をするためのさまざまなデータを取得することができます。
ほかにも、デマンド値が設定値を超えた場合にメールで知らせてくれるアラート機能があり、電気の使い過ぎや契約電力の超過回避に役立ちます。
また、低圧のidemitsuでんきでお客様に提供している「でんきMYページ」も、時間単位・一日単位の使用量や、電気料金の確認が可能です。
再エネ賦課金の仕組みを理解して対策しよう
再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及を目的にすべての電力利用者が負担する費用です。単価は国が定めるためコントロールできませんが、対象となる使用電力量を減らすことで負担軽減することや、電力料金プランの見直しで電気料金負担そのものを見直すことが可能です。自社の状況に合った対策を講じることで、再エネ賦課金によるコスト増を抑えることができます。
出光でんきだからこそ実現できる、お客様のニーズにお応えした電力供給サービスを提案します。